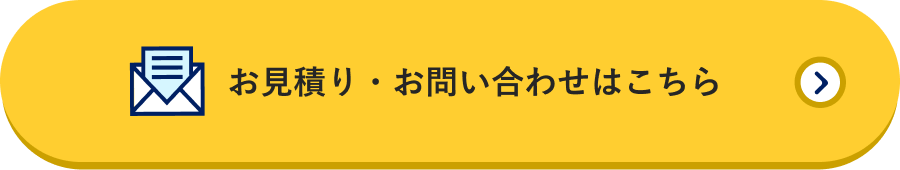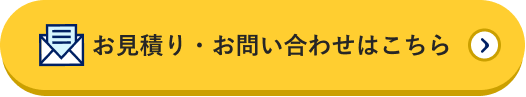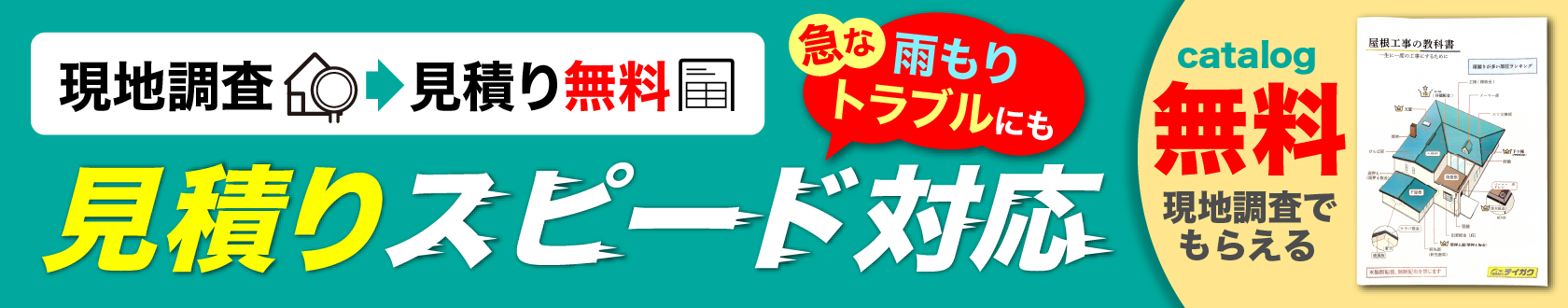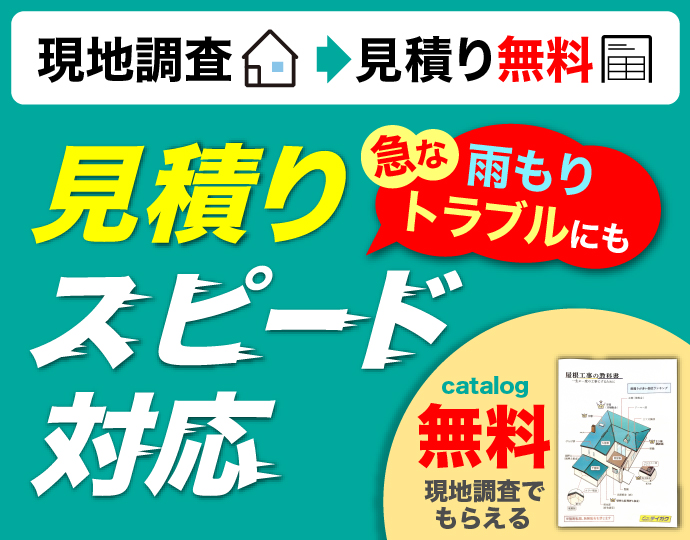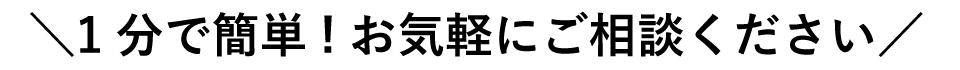屋根はわたしたちの生活を守る大切な部位です。
しかし、日常生活のなかで屋根の状態に気づく機会は少ないです。
そのため、訪問販売業者から指摘を受けてはじめて、自宅の屋根がどんな屋根であり、どんな状況になっているか気づかされるパターンが多いです。
この記事では、戸建て住宅の各屋根材の点検方法やメンテナンス時期についてフォーカスし、解説をします。
屋根のメンテナンス前の準備
屋根のメンテナンスをはかるには、屋根の状態の点検をはじめにおこなう必要があります。
セルフチェックが難しいため、屋根の専門家に訪問してもらい、以下の方法などで屋根の状態を確認してもらいましょう。
ハシゴにのぼって点検

メリット: 最も丁寧かつ確実に屋根の状態を確認できる方法です。微細なひび割れや破損個所も発見できます。
デメリット: 屋根にのぼることは危険であり、二人一組で作業をする必要があります。また、屋根材に損傷を与える可能性もあります。
ドローンを用いて点検

メリット: 安全かつ一人で屋根の状態を確認できます。最近のドローンのカメラは高解像度の画像であり、問題点を確認しやすいです。
デメリット:外観だけの点検であるため、屋根の下地の状態まで把握することができません。操作には一定のスキルと機材が必要です。
伸縮棒による点検
メリット: 高さ6m近く伸びる伸縮棒とデジカメ、そしてスマートフォンを組み合わせて簡単に屋根の撮影ができます。また、安全性が高く、頻繁に行うことが可能です。
デメリット: 屋根全体の撮影が難しく、詳細まで点検をすることができません。
屋根のセルフチェックは難しい
ハシゴやドローン、伸縮棒いずれも点検には設備が必要です。
そして、知識や経験が少ない人が屋根の状態を点検をしても、適切な判断ができません。
そのため、屋根の点検には専門家による評価が不可欠です。
表面的な損傷だけではなく、隠れた問題や将来的かつ潜在的な問題も見つけてくれるはずです。
屋根材ごとのメンテナンス時期
半永久的に維持できる屋根材は存在しません。
そのため、屋根材ごとの耐用年数にあわせて適切な時期にメンテナンスをおこなう必要があります。
瓦屋根

瓦屋根のメンテナンス時期とリフォーム方法
瓦屋根そのものの耐久性は50年近くあります。
しかし、古い瓦は地震や台風の際にずれることがしばしばあります。
特に自然災害発生の後は、屋根の状態を確認してほしいです。
定期的な点検としては、15年~20年に一度が目安です。
屋根にのぼって漆喰の塗り直しや棟瓦の積み直し、あるいは葺き替え工事を検討してほしいです。
漆喰の補修
瓦屋根の漆喰は、屋根の耐久性と調湿性に関わる役割を果たします。
点検後、必要に応じて漆喰の塗り直しをしてほしいです。
棟瓦の積み直し
昔の棟瓦は漆喰とステンレスの番線で固定されています。
そのような固定方法では、地震や台風で崩れやすいです。
そのため、最近の棟瓦はビスで固定することが義務化されています。
金具を用いた棟瓦の積み直し、もしくは屋根の葺き替えを検討してください。
葺き替え
雨漏りや自然災害の被害が生じた場合は、葺き替え工事を検討してください。
瓦そのものは耐久性が高く長持ちしますが、築後30年以上経過している場合、屋根内部のルーフィングや野地板などの劣化が進んでいる可能性があります。
スレート屋根

スレート屋根のメンテナンス時期とリフォーム方法
スレート屋根やアスベストがある商品とない商品で大きく耐用年数が変わります。
定期的な点検としては、15年~20年に一度、屋根にのぼるかドローンなどを用いた点検をおこなってください。
テイガクが推奨するメンテナンス時期は以下の通りです。
スレート屋根のメンテナンス時期
| 世代(年代) | 耐用年数 | 代表的な商品 |
|---|---|---|
| アスベスト含有商品(~1990年代前半) | 40年 | ニューコロニアル |
| アスベストを取り除いた直後の商品(1990年代前半~2000年代半ば) | 20年 | コロニアルNEO |
|
アスベストを取り除いた直後の商品を改良させた商品 (2000年代半ば以降) |
30年 | コロニアルクァッド |
スレート屋根の塗装
色あせした時期がスレート屋根の塗装時期です。
おおむね10年~15年に一度、塗装メンテナンスをおこないます。
ただし、アスベストが含まれてないスレート屋根、なかでも1990年代前半~2000年代半ばに製造されたぜい弱なスレート屋根は塗装をしないでください。
なお、屋根塗装だけをおこなうことは稀です。
外壁塗装や棟板金の交換と同時におこなうことがほとんどです。
棟板金の交換
スレート屋根で最も不具合が多いのが棟板金です。
築後1年の建物でも棟板金ははがれてしまいます。
はがれる理由は強風です。
最低でも10年に一度は点検、必要に応じでメンテナンスをおこないます。
テイガクでは棟板金の下地として、金属下地(エスヌキ)を推奨しています。
風に強く棟板金を固定させる力が長期にわたり維持できます。
![]() テイガクが推奨する金属下地(エスヌキ)の強度について
テイガクが推奨する金属下地(エスヌキ)の強度について
テイガクが推奨する金属下地(エスヌキ)は「価格の安いガルバ」と「錆に強いアルミ」の2種類からお選び頂けます。
アルミは、異種金属接触の腐食を考慮した板厚(1.3mm)で設計し、表面にはアルマイト処理(絶縁処理)を施しています。
これまでの数多くの失敗と経験から生まれたテイガクのオリジナルの下地材です。
詳細はこちら
屋根カバー工法の時期
屋根の耐用年数が過ぎてしまうと、野地板の腐食や雨漏りの発現などが影響し、屋根カバー工法ができなくなってしまいます。
したがって、屋根の耐用年数が過ぎる前に屋根カバー工法は実施してください。
テイガクで屋根カバー工法をおこなうお客様のボリュームゾーンは以下の通りです。
| 世代(年代) | 屋根カバー工法のタイミング |
|---|---|
| アスベスト含有商品(~1990年代前半) | 30~40年 |
| アスベストを取り除いた直後の商品(1990年代前半~2000年代半ば) | 10~20年 |
| アスベストを取り除いた直後の商品を改良させた商品(2000年代半ば以降) | 10~25年 |
葺き替えの時期
原則、屋根そのものの耐用年数のタイミングが葺き替えの適切な時期です。
| 世代(年代) | 屋根葺き替えのタイミング |
|---|---|
| アスベスト含有商品(~1990年代前半) | 35~40年 |
| アスベストを取り除いた直後の商品(1990年代前半~2000年代半ば) | 15~25年 |
| アスベストを取り除いた直後の商品を改良させた商品(2000年代半ば以降) | 20~30年 |
金属屋根

金属屋根のメンテナンス時期とリフォーム方法
金属屋根はトタン屋根とガルバリウム鋼板屋根で大きく耐用年数が変わります。
また、お住まいの環境(沿岸地域や工場地域であるか)によっても屋根の傷み具合が変わってきます。
定期的な点検のタイミングの目安を下記に示します。
金属屋根の点検のタイミング
| 素材 | 点検時期 |
|---|---|
| トタン屋根 | 10年ごと |
| ガルバリウム鋼板 | 10~20年 |
| エスジーエル鋼板 | 10~20年 |
金属屋根の塗装
スレート屋根と異なり、金属屋根は定期的な塗装メンテナンスが必要です。
錆びが雨漏りの原因になるからです。
点検後、錆びによる穴あきが発現する前に、錆止めを含む塗装メンテナンスをおこなってください。
ただし、ガルバリウム鋼板はトタンほど頻繁に塗装をおこなう必要がない素材です。
棟板金の交換
棟板金は他の屋根材同様、風で飛ばされる不具合が多い部位です。
木下地の場合は、5~10年ごとにメンテナンスが必要です。
テイガクが推奨する金属製の下地に交換し、棟板金の長期安定化を図ってください。
屋根カバー工法の時期
横葺き屋根は、基本的に屋根カバー工法ができません。
縦葺き屋根は、構造上、屋根カバー工法がおこなえます。
ただし、縦葺き屋根は結露の影響や緩勾配によって水が回ってしまっている悪影響が及んでおり、屋根カバー工法に堪えられない状態になっていることが多いです。
築後20~25年程度までが屋根カバー工法の推奨時期です。
葺き替えの時期
原則、屋根そのもの耐用年数のタイミングが葺き替えの適切な時期です。
| 世代(年代) | 屋根葺き替えのタイミング |
|---|---|
| トタン屋根 | 屋根葺き替えのタイミング |
| ガルバリウム鋼板屋根 | 30~40年 |
アスファルトシングル

アスファルトシングルのメンテナンス時期とリフォーム方法
アスファルトシングルも他の屋根と同様に改良が重ねられ、20年以上昔の商品と現在販売されている商品とでは、品質が異なります。
他の屋根材に比べて安価であるため、20年30年が経過している場合は、部分修理や塗装ではなく屋根カバー工法もしくは屋根葺き替え工事をおすすめします。
金属屋根の点検のタイミング
| 素材 | 点検時期 |
|---|---|
| トタン屋根 | 10年ごと |
| ガルバリウム鋼板 | 10~20年 |
| エスジーエル鋼板 | 10~20年 |
アスファルトシングルの塗装
色あせが気になりだしたら、アスファルトシングルの塗装を検討する時期です。
なお、塗装メンテナンスでアスファルトシングルの耐久性が長くなることはありません。
棟板金の交換
棟板金は他の屋根材同様、風で飛ばされる不具合が多いです。
棟板金の下に敷かれている下地が木下地である場合、5~10年ごとにメンテナンスが必要です。
テイガクが推奨する金属製の下地に交換し、棟板金の長期安定化を図ってください。
屋根カバー工法の時期
おおむね20年~30年の間に屋根カバー工法によるリフォームを検討してください。
最近、テイガクでは築30年近いマンションのアスファルトシングルを改修する機会が増えています。
30年近く経過したアスファルトシングルは、風でちぎれやすくなってます。
屋根葺き替えの時期
35年以上経過しており、かつ屋根の野地板の腐食が認めらる場合は、葺き替え工事をおすすめします。
雨漏りが発生しているアスファルトシングルの野地板は腐食が進んでいることが多いです。
屋根の点検とメンテナンス費用
メンテナンス費用
屋根の点検と費用を示します。
1人でできる作業であるか、半日以上かかる作業であるかかによって、費用は変わります。
| 点検内容 | 費用 |
|---|---|
| 屋根リフォームに伴う見積書提出と合わせた点検費用 | 無料 |
| 屋根にのぼる調査のみ | 2~4万円 |
| 散水試験や赤外線センサーによる雨漏り点検 | 4~7万円 |
| 屋根の応急処置 | 4~6万円 |
| 屋根の部分修理などのメンテナンスを伴う点検 | 5~7万円 |
屋根職人がいる屋根工事業者へメンテナンスを
メンテナンスを先延ばしにするデメリット

屋根の点検とメンテナンスは大事です。
雨漏りが発生した後では、屋根の野地板が腐食し、野地板交換や補強を伴う大規模な修理が必要になる可能性があります。
野地板増し張りではなく、野地板張り替えは、多大なコストを要します。
また、大規模な自然災害の後では、多くの人が同時に屋根の修理を必要とします。
ブルーシートが敷かれた屋根で数か月間過ごすことを迫られるといったニュースがよく報道されています。40年以上経過したスレート屋根やスレート屋根の下地材(野地板やルーフィング)は著しく機能が低下します。
その結果、予想外の追加工事が必要なる場合があります。
これらのリスクを回避するためにも、定期的かつ早期の屋根の点検とメンテナンスをおこなってほしいです。
倉庫がある屋根工事業者へメンテナンスを依頼しましょう

屋根修理業者を見極める方法
屋根のメンテナンスについて解説をしました。
このページをご覧になられた方は、屋根のメンテナンスをどこに頼めばいいか?についても高い関心があると思います。
リフォームを仲介する会社を含め、屋根のメンテナンスを商売にしている会社はたくさん存在します。
わたしたちテイガクは、倉庫を所有し、日々の業務で屋根工事と密接に関わっています。
材料を倉庫に納品させ、専属職人さんが瓦屋根を葺き替えたり、スレート屋根に金属屋根を重ね張りしたりする専門工事業者です。
もちろん、現地調査から雨漏りの点検、火災保険の申請手続き用の見積書の作成まで毎日おこなっています。
直接工事による屋根工事をおこなう私たちのような本当の屋根工事会社に、依頼することをお勧めしたいです。
適正価格かつより専門的な工事の提案を受けられるはずです。
屋根は大切な家族を守る建物で最も大切な部位です。
だからこそ、実績と技術の実力がある屋根工事会社に工事を依頼しましょう。